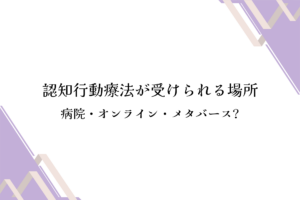うつ病や適応障害の“うつ状態”がなかなか治らない場合、本当の病名は「双極症(双極性障害)」であったのに気づかれずにいたため、ということがよくあります。
双極症とは、気分がハイになる「躁(そう)状態」と、気分が落ち込む「うつ状態」が繰り返される病気です。
かつては躁うつ病などとも呼ばれ、シンプルで誰でもわかりやすそうなこの病気が、実は専門家でさえも見極めの難しい精神疾患のひとつと考えられているのです。
最大の理由として、通常のうつ病でも双極症でも、うつ状態では症状がそっくり同じに見えてしまうため、ということが挙げられます。
しかし、うつ病と双極症では似て非なる別の病気であり、薬の使い方など治療法も大きく異なります。
うつ病には効果的な抗うつ薬が双極症では無効だったり、逆に効き過ぎて躁状態を誘発したり、かえってうつ状態を悪化(長期化・重症化)させることが少なくあいません。
苦しいうつ状態は病的だと自覚しやすいのに対して、ちょっとハイ(軽躁)なくらいだと覚えてすらいないことさえ珍しくありません。
また双極症は他のつらい精神疾患と合併も多いのですが、どうしてもそちらの精神疾患が目立つために、わかりづらい双極症は「じゃない方」扱いされて手つかずのままということも多いのです。
この記事では、双極症とうつ病の違い、診断が遅れる原因、併存症や症例、そして治療・支援の方法までを解説します。
双極症の特徴
双極症は、躁とうつの気分が周期的に繰り返される精神疾患です。
“躁”の状態にもいろいろな出方があり、大きく分けると二つのタイプがあります。
ひとつは気分が上がり活動的・社交的になるタイプ、もうひとつはイライラして怒りっぽくなるタイプです。
重い躁状態では、浪費や衝動的で危険な行動などにつながることもあります。
一方で“うつ”の状態は、みなさんがよくご存知のような、気分が落ち込んだり、意欲や集中力が低下し、疲労感に襲われるなど、元気さが失われます。
さらに、躁とうつが同時に出現することもあり、診断はとても難しくなります。
双極症は、大きく「Ⅰ型(躁状態が激しいタイプ)」と「Ⅱ型(躁状態が軽いタイプ)」に分かれ、特にⅡ型は、“人生の半分をうつで過ごす”と言われるほど、うつ状態の期間が長いことが近年、わかってきています。
双極症とうつ病が間違えられやすい理由
多くの双極症は、最初に現れるのは躁(軽躁)状態ではなく、うつ状態です。
特にⅡ型では軽躁の期間が短く目立たないため、本人や周囲も気づきにくくなります。
そのため、双極症ではなく「うつ病」と診断されてしまうことが少なくありません。
実際には、一生に一度、数日間の軽躁状態しか経験していなくとも、双極症と診断されるのです。
また、通常のうつ病では気分が落ちたままのことが多いのですが、「非定型うつ病」と呼ばれる新型タイプでは、楽しいことがあれば気分が上がり、逆につらいことがあれば強く落ち込む(=気分反応性)という特徴があります。
さらに、典型的なうつ病に多い食欲低下や不眠よりもむしろ過眠や過食が目立ったり、強い疲労感や「見捨てられ不安」など他人の反応を過度に気にする傾向がみられるのも特徴です。
こうした非定型うつ病は、研究によっては半分以上が双極症に含まれると報告されています。
それにもかかわらず、しばしばうつ病や適応障害、時には「性格の問題」と診断されてしまうことが少なくありません。
うつ病の治療で使われる抗うつ薬は、うつ病であれば気分の安定化が期待され、双極症でも短期的にはうつが一時改善することがあります。
しかしその後、躁状態へ移行する「躁転」や、躁とうつが同時に出現する複雑で治療が難しい状態を引き起こしたり、長期的にはうつ状態そのものも悪化(長期化・重症化)させてしまうという報告もあります。
欧米では、正しい診断に行き着くまでに平均で8年かかったという報告もあります。
日本でも、長期間にわたって双極症と診断されずにいる方は少なくないと指摘されています。
さらに、「なかなか治らないうつ病の約3割は実は双極症だった」という報告や、抗うつ薬に反応しにくいうつ病では、その後に双極症と診断されるリスクが約3倍に高まるといった研究もあります。
双極症の診断を遅らせる併存症
双極症はうつ状態がうつ病そっくりだからというだけでなく、ほかの精神疾患を合併しやすいために診断が難しくなることがあります。
特によく合併するのは次のような疾患です。
不安症(パニック症や社交不安症など)
約半数の方に不安症が合併すると報告されています。
不安症の治療には抗うつ薬がよく使われますが、双極症が隠れている場合には症状がかえって悪化することがあります。
不安症と似ていますが厳密には別に分類される強迫症も合併は見られ、不安症と同様に注意が必要です。
摂食障害
摂食障害の合併率は一般の方に比べて数倍高いとされています。
特に過食を主な症状とする過食性障害では、その割合が10倍近くにのぼるとの報告もあります。
過食の治療には抗うつ薬が使われることがありますが、双極症が隠れている場合には、かえって気分が不安定になることがあります。
アルコールや薬物の依存症
双極症とアルコール依存症(大酒家も)には、生物学的共通性も見つかっており、約3割で合併が報告されています。
双極症の治療をきちんと行うことで、飲酒量が減ることもわかっています。
また薬物依存症も多いのですが、特に大麻使用歴は、双極症の発症リスクをおよそ3倍に高めることが証明されており、注意が必要です。
ADHDやASDなどの発達障害(神経発達症)
およそ2~3割にADHD(注意欠如・多動症)が合併すると言われています。
特にADHDのお子さんは、将来、大人になってから双極症を発症するリスクが高く、男子では約8倍、女子では約10倍にのぼるという研究もあります。
ADHDの治療薬の中には、双極症の治療を先に行わないと気分が不安定になりやすいものもあるため、注意が必要です。
また、ASD(自閉スペクトラム症)についても、約3割の方が双極症を合併すると報告されています。
PTSD
双極症の患者さんの半数近くで、子ども時代に虐待などのつらい体験をしていることが報告されています。
そのうち約3割の方はPTSD(心的外傷後ストレス障害)を併せ持つことが知られています。
児童期の虐待は双極症の発症リスクを2倍以上に高め、特に心理的な虐待はほかの形の虐待以上に強く双極症に悪影響をもたらすこともわかっています。
パーソナリティ障害
パーソナリティ障害の合併も少なくありません。
特に、感情や人間関係が激しく不安定な「境界性パーソナリティ障害」は、合併率が約2割にのぼると報告されています。
遺伝的にも共通点があるとされており、一時期、米国精神医学会によって推奨されていた境界性パーソナリティ症治療における抗うつ薬使用が撤回に至った一因にも、この双極症合併の多さがあったとされています。
こうした合併がある場合、とくにうつ(躁)状態のときにだけ不安や過食、ADHDなどの症状が悪化することがあります。
このようなケースでは、抗うつ薬やADHD治療薬を使う前に、まず双極症の治療を行って気分を安定させることで、これらの症状が消えたり、かなり落ち着くことも少なくありません。
しかし実際の医療現場では、多くの患者さんが「苦しいパニック症状を一刻も早くどうにかしてほしい」「まず過食をなんとかしたい」「ADHDの症状を最優先で改善したい」というニーズが強く、それらの治療が優先されがちです。
その結果、まず抗うつ薬やADHDに対する中枢刺激薬などが使われ、かえって気分だけでなく合併症の症状まで一緒に悪化する場合も少なくありません。
私自身は、原則的にはまず双極症の気分を安定化させ、そのうえで必要に応じて最小限の薬物療法を追加する方が、結果的に全体の症状安定化につながることが多いと印象を有しています。
双極症に気づくためのサイン
自分の過去の行動を振り返ることが、早期発見につながることがあります。
かつて一度でも、次のような躁(軽躁)の状態を、数日間以上経験したことはないでしょうか?
- いつもよりおしゃべりや早口になったり、声が大きくなった
- 電話や連絡を立て続けにしていた
- 寝る間も惜しんで活動的だった(睡眠時間が短くても平気だった)
- 気が大きくなりふだんなら買わない高価な買い物をしていた
- ふだんより服装や化粧が派手になっていた
- イライラしやすく怒りっぽくなった
- クリエイティブなアイデアが湧き、頭の回転が早くなった
- なんでもできるような過剰な自信や万能感があった(周囲を見下すような気持ちになった)
- 異性関係が奔放になった
双極症(双極性障害)の治療と再発予防
双極症の治療では、薬物療法が前提となりますが、症状を安定させるためには心理社会的アプローチを組み合わせることが推奨されています。
薬物治療としては、気分安定薬(リチウム、ラモトリギンなど)や非定型抗精神病薬(オランザピンなど)が中心であり、症状や経過に応じて主治医と相談しながら他の薬剤が組み合わされます。
心理的アプローチも重要で、再発リスクを半減させることが示されています。
代表的なのは考え方や行動を振り返る「認知行動療法」です。
ただし誤解されがちなのは、“うつ病”の認知行動療法と双極症の認知行動療法は、重なる部分もある一方で基本構造は大きく異なるという点です。
そのため、うつ病のやり方をそのまま適用すると、かえって双極症を不安定化させてしまうことも報告されています。
さらに、日本の健康保険制度では「気分障害」のうち認知行動療法が適用されるのは「うつ病」に限られており、双極症に対する認知行動療法はまだ認められていません。
双極症の心理的アプローチを専門的に行える実施者も、国内ではまだ多いとは言えないのが現状です。
一方で、一人で手軽に取り組みやすい方法としては、医学的根拠に基づき、今日からでも始められる「社会リズム療法」があります。
これは、毎日の起床・就床時刻、その日の主活動の開始時刻、最初に誰かと接触した時刻、そして夕食時刻という5つの生活リズムを一定に保つことで、不規則な生活に弱い双極症の再発を予防できることが示されています。
私たちが作成した非商用の無料アプリ「ココロのリズム」も、日本うつ病学会の公式ホームページからアクセス可能ですので、ぜひご利用ください。

関連記事:認知行動療法(CBT)とは?やり方・受けられる場所などを解説
関連記事:認知行動療法が受けられる場所|病院・オンライン・メタバースなどそれぞれの特徴とは?
まとめ
双極症はうつ病と似た症状を示すため診断が難しく、特にⅡ型は見逃されやすい病型です。
症状の悪化やさまざまなリスクを防ぐためには、正しい診断と適切な薬物療法が欠かせません。
さらに、生活リズムを整えることや、心理社会的な支援(とくに社会リズム療法)を組み合わせることで、再発を防ぎ、予後や生活の質を大きく改善できる可能性があります。